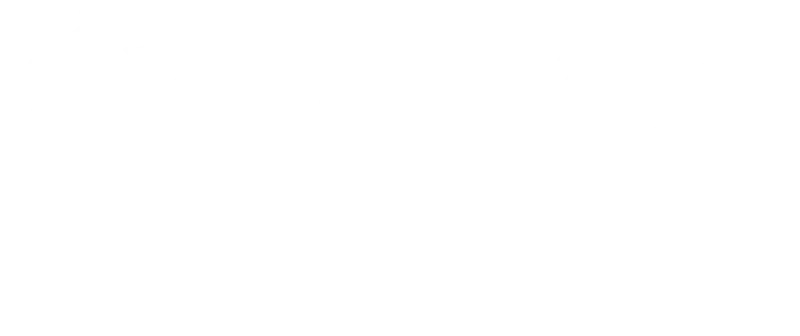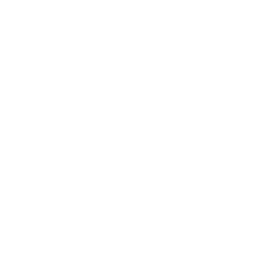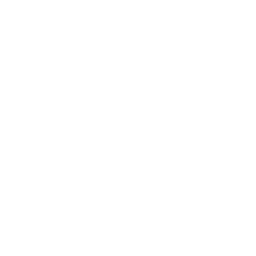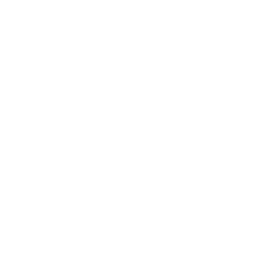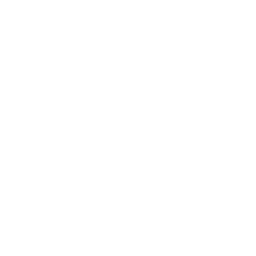鮎の匂いはスイカに似ている?香りの特徴と匂いを決める要因を解説

夏の風物詩として親しまれている鮎は、清流の中を泳ぐ美しい姿や繊細な味わいから多くの人に愛されています。なかでも、体から放たれる爽やかな香りは他の魚にはない鮎ならではの魅力です。魚は生臭いものとされる中、なぜ鮎だけが良い香りを漂わせているのでしょうか。
本記事では、鮎の匂いの特徴や「香魚」と呼ばれるようになった理由について詳しく解説します。また、独特な香りを放つ原因についても紹介しているので、鮎の香りに関心がある方はぜひ参考にしてください。
この記事を読むための時間:3分
鮎が「香魚」と呼ばれる理由
鮎は「年魚」や「銀口魚」の他に、「香魚」という別名を持っています。美しい名前が付けられたのは、鮎の体から爽やかでみずみずしい芳香が漂うためです。中でも、旬を迎える7~8月に獲れる若鮎は、他の時期に獲れるものと比べて香りが一層際立っています。また、生の鮎だけでなく炭火で塩焼きにした後でも、鮎の爽やかな香りは失われず、香ばしさの中にほんのりと漂い、鮎特有の風味を際立たせてくれます。
鮎の匂いの特徴
鮎の香りを表現する際によく使われるのが、スイカやキュウリのような香りです。特に釣ったばかりの鮎からは、夏野菜を思わせるような爽やかな香りが漂います。香りは鮎の成長段階や鮮度によって変化するとされており、初夏に獲れる新鮮な若鮎ほど強い香りを持ちます。さらに香りの質も異なり、清流で育った稚魚や若鮎からはスイカの香りが、その他の鮎からはキュウリの香りがするといった違いもあるようです。
鮎の匂いに影響する要因
鮎の香りは、さまざまな要因によって左右されます。中でも、食べているものと生育環境が香りの質と強さに大きく影響を与えるとされています。そのため、同じ種類の鮎であっても住んでいる場所が異なれば香りにも違いが生まれるのです。以下では、鮎の香りに影響を与える2つの要因について詳しく紹介します。
食べているもの
鮎の香りに最も大きな影響を与えるのが、日頃から摂取している食べ物です。鮎は川底の石に生える苔(藻類)を主食としており、この植物性の食べものが鮎特有のすっきりとした香りを生み出す原因です。藻類にはさまざまな種類があり、それぞれ異なる香りを作り出すため、同じ種類の鮎でも生息する川によって放つ香りが異なります。
さらに、鮎は成長段階によって食べる餌の種類や量が変化するため、同じ場所に生息していても時期によって香りの強さや質に差が出ることがあります。例えば、夏の若鮎からは強い香りが漂う一方で、秋になって落ち鮎になると徐々に香りが弱まります。
生育環境
鮎の香りに影響を与える2つ目の要因は生育環境です。水が澄んでいる清流では、良質な藻が育つため、鮎の香りも強くなる傾向にあります。そのため、綺麗な川と淀んだ川はもちろん、同じ川でも澄んだ水が多い上流とさまざまなものが混ざる下流とでは、香りの質や強さに差が出ることがあります。
また、天然か養殖かも香りに影響を与える要因になります。鮎は苔を食べることで爽やかな香りを放つようになるため、人工飼料で育つ養殖鮎は天然鮎ほど香りが強くありません。そのため、養殖鮎には餌に藻類を混ぜるなどの工夫が施される場合があります。
匂いも楽しみながら鮎料理を味わおう
本記事では、鮎の匂いの特徴や「香魚」と呼ばれるようになった理由、さらに独特な香りを放つ原因について解説しました。鮎の魅力は、さっぱりとした白身の旨味だけでなく、体から放たれる爽やかな香りにもあります。そのため、鮎をより深く楽しむには、香りにも注目しながら味わうことが大切です。
調理する際は、塩焼きや鮎飯など、香りを活かした方法で調理してみると良いでしょう。次に鮎を味わう際は、見た目や味だけでなく、ぜひ香りにも意識を向けてみてください。