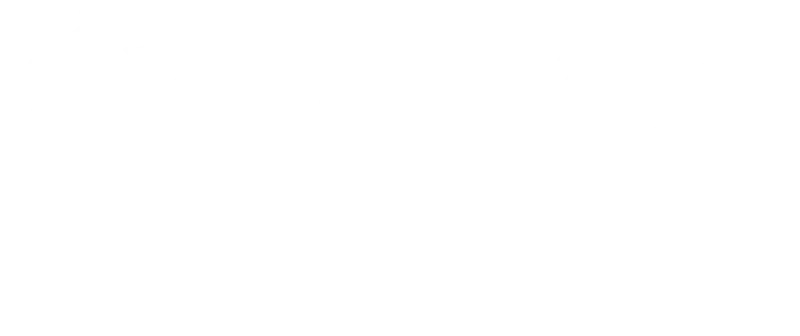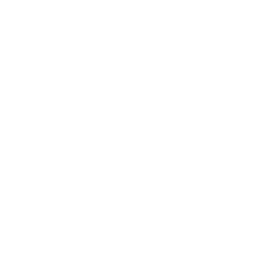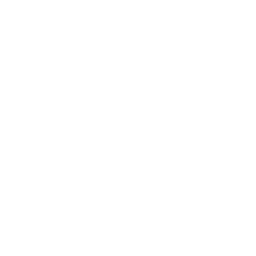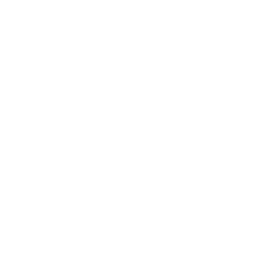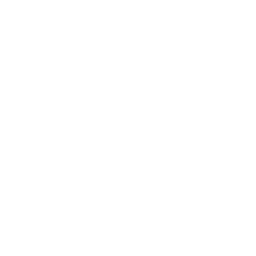鮎の旬はいつ?天然鮎が美味しい時期と全国の有名産地を詳しく紹介

夏になると清流の近くでは、鮎釣りや鮎の掴み取り体験などが行われ、多くの人で賑わいます。スイカやかき氷と並び夏の風物詩として親しまれている鮎は、爽やかな香りと上品な味わいが特徴の川魚です。日本各地に生息しており、地域ごとに異なる風味を楽しめるのも鮎の魅力です。
本記事では、夏の味覚として親しまれている鮎について理解を深めるために、旬の時期や成長過程について詳しく解説します。さらに、日本各地の代表的な天然鮎と養殖鮎の産地も紹介しているので、鮎を選ぶ際の参考にしてください。
この記事を読むための時間:3分
鮎の旬の時期
夏の風物詩とも言われる鮎の旬は、6月~8月にかけてです。そのため、6月の上旬になると全国各地の川で鮎釣りが解禁され、多くの釣り人が集まります。旬の鮎は脂がよくのっており、1年の中でも特に美味しいとされる時期です。鮎特有の爽やかな香りも一層際立ち、口の中に広がる風味は別格です。特に7月頃に獲れる若鮎は骨まで柔らかく、塩焼きや天ぷらにすれば、鮎の旨味を余すことなく味わえます。
鮎の成長過程
鮎は「年魚(ねんぎょ)」とも呼ばれ、1年で一生を終える魚です。冬に生まれ、翌年の秋に産卵して一生を終えるため、季節の移り変わりとともに成長していきます。また、1年という短い一生の中で川と海を行き来するという特徴もあります。以下では、鮎の成長と生活環境の変化について季節ごとに解説しています。旬の鮎をより深く理解するためにも、鮎の生涯を見ていきましょう。
冬
秋に川の下流で産卵された鮎の卵は、冬の寒い時期は冷たい川底で静かに孵化の時を待ちます。卵からかえるまでの期間は水温によって異なり、水温が高いほど早く孵化する傾向にあります。一般的に水温が18℃の場合、孵化するまでにかかる期間はおよそ2週間です。
孵化したばかりの鮎の赤ちゃんは、まだ自力で泳ぐ力がなく、川の流れに乗って海へと運ばれていくのですが、海まで無事にたどり着けるのは全体の3~5割程度とされています。海に到着した鮎の赤ちゃんは、浅瀬でプランクトンを食べながら成長していきます。
春
春になると稚魚に成長した鮎は河口付近に集まり、川を遡上する準備を始めます。プランクトンを食べて体を大きくしながら、川の水に馴染むよう海水から淡水に適した体に仕上げていくのです。水温の上昇とともに、稚鮎は上流を目指して川を遡上し始めます。海ではプランクトンを食べていましたが、川を登り始めるとすぐに藻類を食べるようになります。
夏
夏は鮎が最も活発に動く時期です。川底に生えている藻を食べて大きく成長する季節でもあり、6~7月頃には体長15cmほどの「若鮎」となります。初夏に獲れる鮎は骨がまだ柔らかいため、塩焼きや天ぷらにして丸ごと食べるのに適しています。
7~8月にはさらに成長し、体長は25cm前後になります。鮎特有の爽やかな香りが一層強くなり、速い川の流れの中で育った身は引き締まり、脂ものって、まさに最も美味しい時期です。
秋
夏の終わりから秋にかけて、鮎は産卵の準備を始めます。この時期の鮎は「子持ち鮎」や「落ち鮎」と呼ばれ、夏の爽やかな風味とは異なり、より濃厚な味わいを楽しめます。川の上流に生息していた鮎は、卵や白子が成熟すると川を下り、下流付近で産卵を行います。卵を産み終えた鮎は、1年という短い生涯を静かに終えるのです。

日本国内の有名な鮎の産地
日本には数多くの清流があり、それぞれの川に天然の鮎が生息しています。また、各地では地域の自然環境を活かした鮎の養殖も盛んに行われています。地域によって風味や香りが少しずつ異なるのも、鮎の大きな魅力と言えるでしょう。以下では、日本国内の代表的な天然鮎と養殖鮎の産地について詳しく紹介します。
天然鮎の産地
水質の良い川を好む魚として知られている鮎は、日本各地の清流で見られます。川ごとの水質や藻の種類によって風味にも個性が生まれ、産地ごとに特徴が異なります。以下は、都道府県別天然鮎の漁獲量ランキングです。
- 1位 滋賀県 315トン
- 2位 茨城県 309トン
- 3位 栃木県 299トン
- 4位 神奈川県 231トン
- 5位 岐阜県 208トン
以下では、漁獲量にかかわらず天然鮎の産地として有名な川について詳しく紹介します。
熊本県の球磨川
球磨川は「日本3大急流」の1つとして知られている九州を代表する清流です。球磨川の激しい流れの中で育つ鮎は身が引き締まり、食感がしっかりしているのが特徴です。尺アユとも呼ばれサイズが大きく、炭火で塩焼きにすると力強く豊かな風味が際立ちます。
高知県の四万十川
水の透明度が高いだけでなく、瀬と淵が多い地形により豊富な餌場がある四万十川は、鮎の生息環境として優れています。水と藻の質が良いため、香り高く上品な風味が特徴的です。また、四万十川では「友釣り」や「火振り漁」など、伝統的な漁法が残っており、夏の風物詩として地元の人たちだけでなく観光客にも人気があります。
島根県の高津川
高津川は、日本全国でも1位2位を争うほどの水質の良さを誇ります。水の透明度が高いため藻の質も良く、繊細な風味を持つ鮎が獲れることで有名です。旬の時期でも余分な脂がのっていないためさっぱりとしており、わたのほろ苦さが強調され料理のアクセントになります。塩焼きや素焼きの他に、炊き込みご飯の中に入れるのもおすすめです。
秋田県の阿仁川
東北地方の清流として知られる阿仁川の鮎は、サイズが大きく身が引き締まっているのが特徴です。川の途中にある根小屋堰堤を越えなければ上流に行けないため、過酷な自然環境の中で育った鮎は生命力が強く、味にも力強さがあります。しかし上流は渓谷になっており、鮎だけでなく人間が立ち入るのも困難な環境のため、阿仁川で獲れる鮎の漁獲量は非常に少なく、全体の0.1%にも満たないとされています。
滋賀県の姉川
琵琶湖に繋がる姉川で獲れる鮎は、比較的小ぶりで、大きいものでも体長が12~14cmほどしかありません。スイカのような爽やかな香りが漂い、身や骨が柔らかく、しっとりとした食感が特徴です。サイズが小ぶりなため、塩焼きや天ぷらにして丸ごと食べることで、鮎の風味をより楽しめます。
養殖鮎の産地
天然鮎の人気は根強いですが、安定した品質を継続して提供できる養殖鮎も広く親しまれています。近年では、各地域の自然環境を活かしたり、餌や水温管理などに工夫を凝らしたりすることで、香りや味に個性を持たせたブランド鮎も生産されています。例えば、滋賀県の「コアユ」や愛知県の「ハーブ鮎」などが有名です。
環境が整えられた養殖では、安全性の高い鮎の生産が行えるため、安心して食べられると家庭や飲食店で多く消費されています。以下は、都道府県別養殖鮎の漁獲量ランキングです。
- 1位 愛知県 1,247トン
- 2位 岐阜県 838トン
- 3位 和歌山県 580トン
- 4位 栃木県 308トン
- 5位 滋賀県 271トン
季節や産地ごとに異なる鮎の味わいを楽しもう
本記事では、鮎の旬の時期や成長過程、そして日本各地の代表的な産地について紹介しました。鮎は、季節や育った環境によって香りや味わいが大きく変わる、非常に繊細な魚です。脂がのった旬の鮎はもちろん、骨まで柔らかく丸ごと食べられる若鮎や、濃厚な旨味が楽しめる子持ち鮎など、時期によってさまざまな魅力があります。
地域ごとの風味の違いにも注目することで、より一層鮎の美味しさを味わえるでしょう。ぜひ、今回紹介した内容を参考に季節や産地を意識しながら選び、鮎の奥深い味わいを楽しんでみてください。