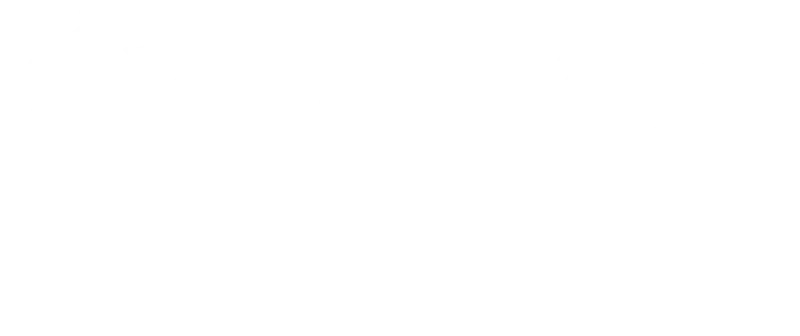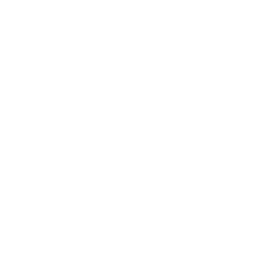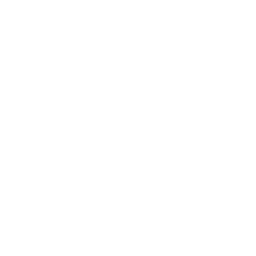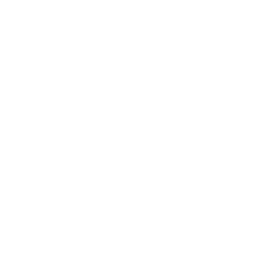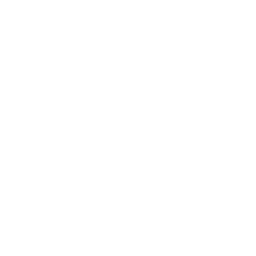川魚はなぜ臭い?臭いの原因と養殖の川魚がおすすめの理由も解説

調理前の川魚に独特の「川臭さ」や「泥臭さ」を感じたことがある方も多いのではないでしょうか。実は川魚の臭いは、魚そのものが原因ではなく、生活している環境や食べているエサに由来するものです。そこでこの記事では、川魚が臭い原因を解説します。養殖の川魚がおすすめの理由もあわせて解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事を読むための時間:3分
川魚はなぜ臭いのか
川魚の「臭い」とされるものの正体は、主に水中の藻類やプランクトンが出す化学物質です。たとえば、藍藻類や一部の微細藻類が放つ「ジェオスミン」や「2-メチルイソボルネオール」という成分が、泥臭さやカビ臭さの元になります。臭いの元となっている成分が、魚の体表・エラ・内臓に付着したり、皮下脂肪に蓄積されたりすることで、人間の嗅覚に感じやすくなります。
特に、夏場や水温が高くなる季節には藻類が増殖しやすく、臭いが強くなりやすいです。また、川の水質が濁っていたり、流れが滞っていたりする場所では、より多くの微生物が繁殖し、魚への臭い移りが進みやすくなります。
川魚の身自体はあまり臭くない
実は、川魚の身そのものには強い臭いはほとんどありません。臭いの多くは皮・血合い・内臓・エラといった部分に集中しています。そのため、適切に下処理を行うことで、かなりの臭いを取り除けるでしょう。
たとえば、調理前に塩を振って10分程度置き、余分な水分とともに臭みを抜いたり、酢水や酒に漬け込んで臭い成分を中和したりする方法が効果的です。また、熱を通すことで気になる臭いの多くは飛ばせるため、煮魚や唐揚げなど火を通した料理では気にならないケースも多くあります。
下処理の際には、できるだけ血合いやエラを丁寧に取り除き、流水でしっかりと洗うことが重要です。これだけでも、臭いを大きく軽減できます。ただし、生食や淡い味付けで提供する場合には、もともと臭いの少ない魚を選びましょう。
養殖の川魚があまり嫌な臭いがしない理由
養殖の川魚があまり嫌な臭いがしない理由は、以下の2つです。
- 水質を管理しているから
- 臭いを抑えられる成分をエサに混ぜているから
水質を管理しているから
川や湖の自然環境と異なり、養殖施設では水の流れ・温度・酸素濃度・濁り具合などを常にモニタリングし、最適な状態に保つように設計されています。さらに、ろ過装置を使って有機物や藻類を取り除いたり、水換えの頻度を増やしたりしていることも大きなポイントです。ろ過や水換えにより、臭いの原因となる成分をできるだけ発生させないようにしています。
臭いを抑えられる成分をエサに混ぜているから
養殖魚には、天然の川魚とは異なる栄養設計された飼料が与えられています。飼料には、魚の成長や健康をサポートする成分だけでなく、臭いの原因物質を抑制する成分も含まれている場合があります。
たとえば、活性炭や植物由来の天然抽出物を飼料に混ぜることで、腸内のアンモニアや臭気物質の発生を抑えたり、体内での蓄積を防いだりする効果が期待できるでしょう。エサを工夫することにより、養殖魚は特有の川臭さがほとんどしない、食べやすい魚に育てられています。
養殖の川魚は嫌な臭いがしないものが多くておすすめ
川魚の「臭い」が気になる方には、養殖された鮎やニジマスなどがおすすめです。養殖の川魚であれば、水の管理やエサの工夫がされているため、天然の魚に比べて臭いが少なく、食感や風味も安定しています。
特に鮎は、養殖でもスイカのような香りを持つ「香魚」として人気が高く、塩焼きや天ぷらにすると素材の良さが際立つでしょう。ウナギも、養殖物であれば泥抜きがしっかりと行われており、臭みがなく食べやすいです。川魚に苦手意識がある方も、ぜひ1度、養殖の川魚を試してみてはいかがでしょうか。